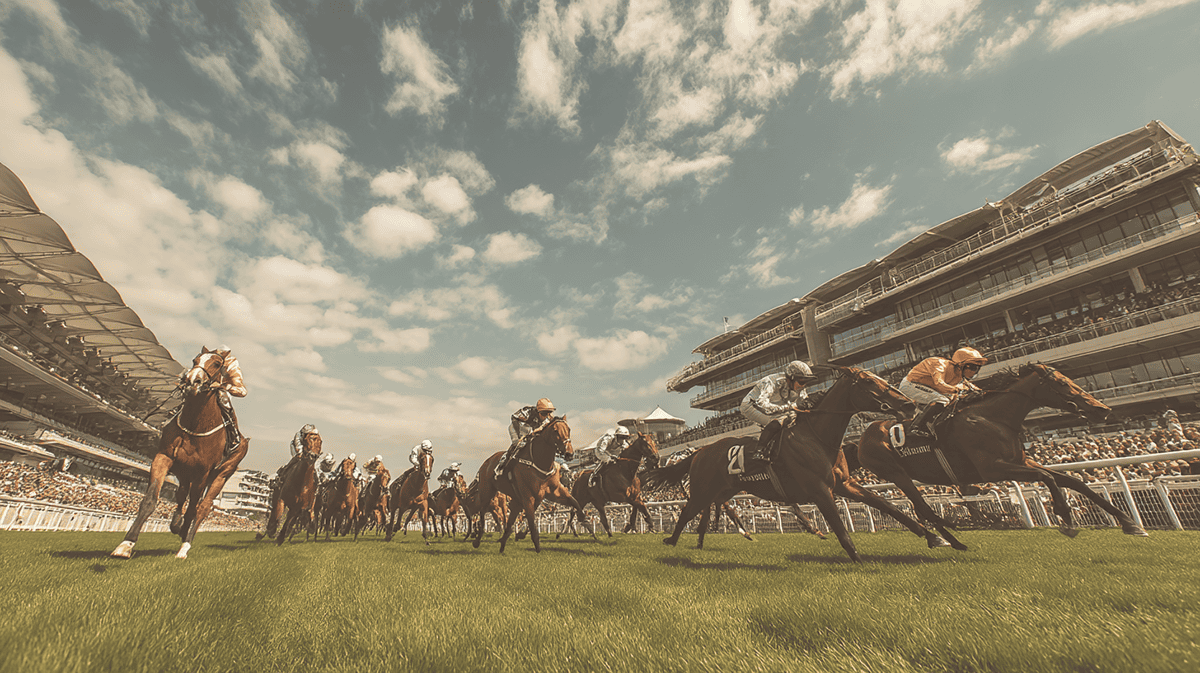競馬を始めたばかりの方にとって、「馬連と枠連の違い」は非常にわかりづらいテーマです。「馬連とは何か」「枠連とはどう違うのか」といった基本から、実際にどの馬券を買えばよいか判断するのは簡単ではありません。さらに「ワイド」や「枠連ボックス」「枠連単 枠連複 違い」など、用語も多く混乱しやすいのが現実です。
この記事では、そんな初心者の方にも分かりやすく、馬連と枠連の仕組みや違いを丁寧に解説していきます。どちらが当たりやすいのか、どちらが最強なのか、収益性や予想のしやすさを踏まえた比較も行います。
また、「枠連を買う人」はどんなタイプなのか、「枠連のメリット」は何かといった観点から、あなたに合った馬券の選び方もご紹介します。今後の競馬をより楽しむために、まずは馬券の基本を正しく理解しておきましょう。
- 馬連とは何か、どのように当てるか
- 枠連とは何か、馬連との仕組みの違い
- 馬連・枠連・ワイドの使い分け方
- 枠連のメリットや購入パターン
馬連と枠連の違いを初心者にも分かりやすく解説
馬連とは?当たり方と基本ルール

馬連(ばれん)は、2頭の馬の「組み合わせ」を予想する馬券です。レースで1着・2着に入る馬を順不同で当てることができれば的中となります。
馬連の基本ルールはとてもシンプルです。1着と2着になる馬の「番号を両方当てる」という形式であり、順番は関係ありません。例えば、3番と7番の馬を馬連で購入し、レースでこの2頭が1着・2着に入れば、3→7でも7→3でも当たりになります。
なぜ初心者にとって理解しやすいかというと、当てるための条件が明確だからです。複雑な選択肢やフォーメーションを考えなくても、2頭の強そうな馬を選べば良いため、競馬の入口としては適しています。
以下に、馬連の特徴をまとめた表を示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 的中条件 | 1着・2着の馬を順不同で当てる |
| 購入単位 | 1点100円(最低金額)から |
| 配当傾向 | 本命同士だと安く、穴馬絡みで高配当 |
| 初心者向け | 比較的わかりやすく、選びやすい |
ただし、注意点もあります。馬連は「2頭とも上位に来る」必要があるため、1頭が3着以下になっただけで不的中になります。想定より強い馬が出てきた場合や、道中の展開に左右されやすいという点にも注意が必要です。
このように、馬連は競馬初心者にとって理解しやすい馬券ですが、2頭とも好走しなければ的中しないというリスクもあることを覚えておきましょう。
枠連とは?馬連との仕組みの差と基本知識
枠連(わくれん)は、「枠番」を使って1着・2着の組み合わせを予想する馬券です。馬の個体番号ではなく、出走馬が配置される「枠」の番号(1枠~8枠)で当たりを判定します。
結論から言えば、枠連は馬連と似ているようで異なる特徴を持っています。枠連は、選んだ2つの枠にそれぞれ1頭ずつ入れば的中です。そのため、同じ枠から1着・2着が出る場合(いわゆる「同枠決着」)でも的中となります。
例えば、1枠と3枠の枠連を買った場合、1枠から1頭、3枠から1頭が1着・2着になれば当たりです。仮に1枠の馬が1着、同じ1枠の別の馬が2着であっても、枠連1-1で的中になります。
馬連と枠連の違いを表にまとめると以下の通りです。
| 比較項目 | 馬連 | 枠連 |
|---|---|---|
| 対象 | 馬番号 | 枠番号(1~8) |
| 的中条件 | 指定した2頭が1・2着(順不同) | 指定した2枠から1頭ずつ1・2着 |
| 同枠決着 | 的中しない | 的中する |
| 精度 | 馬をピンポイントで当てる | 枠単位のためやや広く当たる |
| 配当傾向 | 枠連より高くなりやすい | 馬連より低めになることが多い |
このように、枠連は多少の「ゆるさ」があるため、予想が大きく外れていなければ当たる可能性がある点が魅力です。
一方で、デメリットもあります。特定の馬を狙っていても、同じ枠に入った他の馬が来ることもあるため、思わぬ形で外れることもあります。また、出走頭数が少ないレースでは、枠数自体が限られるため、馬連との違いが小さくなることもあるでしょう。
このように考えると、枠連は初心者にとって比較的当たりやすい選択肢となる一方、狙った馬が来なくても的中する点にやや「もどかしさ」を感じることもあるかもしれません。使いどころを考えたうえで、上手に活用していきたいところです。
枠連単・枠連複・ボックスの違いと使い分け
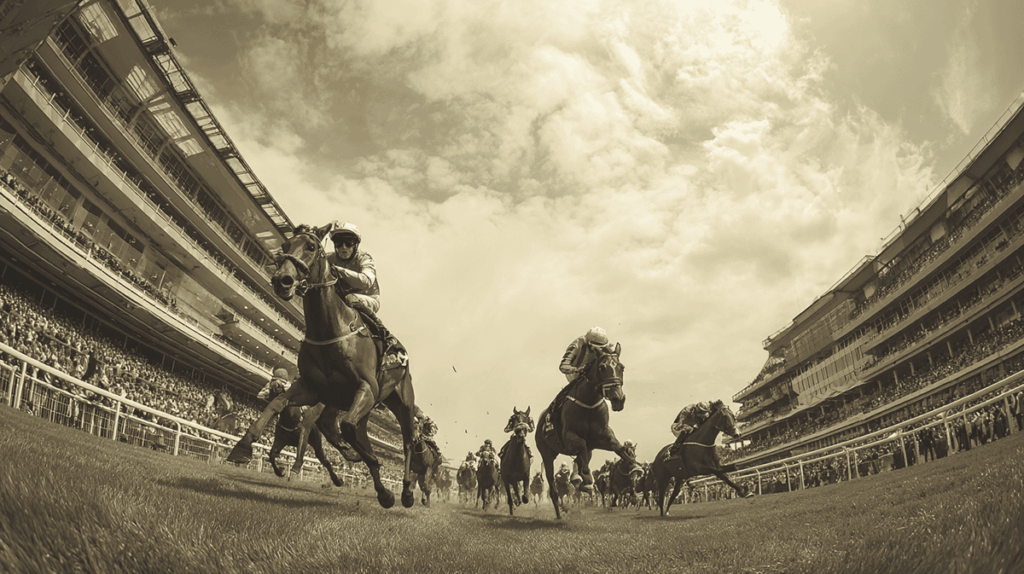
枠連に関する用語は少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的な仕組みを理解すれば難しくありません。
まず「枠連単」ですが、これは正式には存在しない馬券の呼び方で、「馬単」と混同して使われることがあります。つまり、枠連に「順序」を当てる買い方はありません。競馬において「枠連」はあくまで順不同ですので、「枠連単」という表現は誤解を招くため注意が必要です。
次に「枠連複」は、正確には「枠連」と同義です。2つの枠を選び、それぞれから1頭ずつ1着・2着に入れば的中となります。順番は関係ありません。
そして「枠連ボックス」とは、複数の枠を選んで、その中のどの2枠が1着・2着になっても的中とする買い方です。例えば、1枠・2枠・4枠のボックスを購入すると、以下のような6通りの組み合わせになります。
- 1-2
- 1-4
- 2-4
※1-2と2-1は同一とみなされるため、実際の購入点数は「選んだ枠の組み合わせ数」によって決まります。
これらをまとめた比較表は以下の通りです。
| 用語 | 意味・内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 枠連単 | 正式な馬券ではない | 馬単と混同しないよう注意 |
| 枠連(複) | 順不同で2枠を当てる | 一般的な枠連の買い方 |
| 枠連ボックス | 複数枠の組み合わせ全通りをカバーする買い方 | 点数が増える点に注意 |
使い分けのポイントは、買い目の数と予算です。枠連ボックスは広く押さえられる反面、購入点数が多くなりやすいため、資金配分に気をつける必要があります。対して、通常の枠連は点数を絞って高配当を狙いたいときに有効です。
初めてのうちは、ボックスでの購入により感覚をつかみつつ、慣れてきたら状況に応じて絞ると良いでしょう。
枠連のメリットと初心者に向いている理由
枠連は、競馬初心者にとって扱いやすい馬券の一つです。なぜなら、個別の馬を特定しなくても「枠」を予想するだけで当たりになるからです。
馬券には様々な種類がありますが、枠連は「1着・2着の馬が異なる枠に入っていれば的中」というシンプルなルールです。さらに、同じ枠に2頭出走している場合、そのどちらかが絡んでも的中となるため、多少の予想のズレをカバーできる余地があります。
この性質が初心者には特に嬉しいポイントです。競馬に慣れていないと、出走馬の個別能力を見極めるのが難しいため、「枠」でざっくりと当てることができる枠連は安心感があります。
ここでは、枠連の主なメリットを3つに絞ってご紹介します。
- 予想の幅が広い
→ 枠単位で予想できるため、多少のズレが許容される。 - 同枠決着でも的中する
→ 同じ枠の馬が1着・2着になった場合も当たる(馬連は外れ)。 - 買い方がシンプル
→ 枠を2つ選ぶだけでよく、出走表の理解も比較的簡単。
一方で、デメリットも存在します。枠連は、枠ごとの実力差や頭数によって「不利な枠」も存在します。また、枠の並び方や内・外枠の影響もレースによって異なるため、なんとなく選ぶだけでは安定して的中させるのは難しい面もあるでしょう。
このように考えると、枠連は「ある程度の精度で広くカバーしたい」初心者にとって最適な馬券です。まずは少ない点数で試しつつ、枠の傾向や実際の配当を見ながら精度を高めていくと良いかと思います。
ワイドとの違いと初心者向けの選び方
競馬初心者がまず悩むのが、馬券の種類とその選び方です。馬連・枠連・ワイドの3つは、いずれも「2頭を当てる」という点では共通していますが、的中条件やリスク、リターンの面で違いがあります。
それぞれの特徴を、以下の比較表で整理します。
| 馬券種別 | 的中条件 | 特徴 | 初心者向け度 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1着・2着を順不同で当てる | オッズが比較的高い | △ |
| 枠連 | 異なる枠から1・2着を当てる | 枠単位で予想。多少ズレても当たる | ○ |
| ワイド | 選んだ2頭がどちらも3着以内 | 最も当たりやすいが配当は低め | ◎ |
このように、それぞれにメリット・デメリットがあります。
初めて競馬をする場合は、ワイドから始めるのが安心です。なぜなら、的中条件がゆるやかで、予想が外れても3着に入れば当たりになるからです。勝ちやすいことで競馬に対する自信もつきやすく、楽しさも感じやすくなります。
一方で、ある程度馬の実力や展開を予測できるようになってきたら、馬連や枠連にチャレンジするのも良いでしょう。馬連はピンポイントの予想が求められますが、そのぶん配当が高めです。枠連は個別の馬ではなく「枠」で予想するため、初心者にも取り組みやすい中間的な立ち位置です。
このように、自分の経験値や予算、楽しみたいスタイルに合わせて馬券の種類を選ぶことが大切です。まずはワイド、次に枠連、慣れたら馬連、というステップアップもおすすめです。
馬連と枠連の違いを理解して最適な馬券を選ぶ
どちらが当たりやすく稼ぎやすい?収益性比較

馬連と枠連は似たような見た目ですが、当たりやすさや収益性には明確な違いがあります。それぞれの性質を理解しておくことで、より賢い馬券選びが可能になります。
まず、当たりやすさについて比べてみましょう。
- 馬連は「2頭の馬」が1・2着に入る必要があります。
- 枠連は「2つの枠」から1頭ずつ1・2着に入ればOKです。
つまり、枠連のほうが的中範囲が広く、相対的に当たりやすいです。同じ枠に複数の馬が出ている場合、そのどれが来ても当たるため、多少の読み違いがカバーされることもあります。
一方で、収益性(配当)を見てみると、馬連の方が高くなる傾向があります。これは、的中条件が厳しい分、オッズが上がりやすいためです。
| 比較項目 | 馬連 | 枠連 |
|---|---|---|
| 的中率 | やや低い | やや高い |
| 配当傾向 | 高め | 低め |
| 難易度 | 馬を正確に当てる必要あり | 枠単位で予想できる |
ここから考えると、「安定して当てたい」なら枠連、「高いリターンを狙いたい」なら馬連が適しています。特に、初心者がいきなり馬連で大きな配当を狙おうとすると、的中率が低く続けづらくなる可能性もあるため、最初は枠連から始めて、徐々に馬連に移行するのも一つの方法です。
収益性を重視するなら、人気馬同士の組み合わせではなく、穴馬を絡めた買い方を研究してみるのも良いでしょう。ただし、当たりにくくなるリスクは常にあるため、自分の予算と相談しながらバランスを取ることが重要です。
買う人の傾向と実際の使い分け方
馬連や枠連を選ぶ人には、それぞれに共通した特徴があります。どちらを選ぶかは、競馬経験や予想スタイルによって異なるため、まずはその傾向を理解しておくことが重要です。
馬連を買う人の多くは、ある程度競馬に慣れていて、馬の能力や展開を細かく分析する傾向があります。具体的には、「この2頭が明らかに強い」と確信を持てるケースで馬連を使うことが多いです。リターンの高さを重視し、的中率よりも収益性を狙いたい人に向いています。
一方で、枠連を選ぶ人は、馬よりも「枠の流れ」や「脚質傾向」に注目します。特に、出走頭数が多くて予想が難しいレースや、人気馬が同じ枠に集中しているときなどに枠連が選ばれやすいです。また、同じ枠の馬が両方好走することも想定しているため、やや安全志向のユーザーに支持されやすい馬券です。
以下に使い分けの一例をまとめます。
| 状況・傾向 | 適した馬券 |
|---|---|
| 馬の能力を細かく分析したい | 馬連 |
| 予想に自信がある | 馬連 |
| 枠単位でざっくり狙いたい | 枠連 |
| 人気馬が同じ枠に入っている | 枠連 |
| 展開が読みにくい大混戦のレース | 枠連 |
こうして見ると、予想の「精度」と「幅」に応じて馬連と枠連を使い分けることが、的中率と収益性のバランスをとるために重要であることがわかります。無理に一つに絞らず、レースごとに最適な選択を心がけましょう。
初心者が最初に覚えるべき馬券の選び方

競馬初心者がまず覚えるべきなのは、「当たりやすく、理解しやすい」馬券の種類です。いきなり複雑な買い方をすると混乱しやすく、競馬の楽しさを感じる前に挫折してしまうこともあります。
そのため、最初におすすめしたいのは「ワイド」です。ワイドは、選んだ2頭がともに3着以内に入れば当たりとなるため、非常に的中しやすいのが特徴です。馬券の当たりを一度経験することで、競馬に対する興味や理解も深まりやすくなります。
次に覚えたいのが「枠連」や「馬連」です。これらは1・2着を当てる必要がありますが、ワイドに慣れてきた段階で挑戦すると、買い方や予想の精度を徐々に高めていくことができます。
初心者に向けた段階的な馬券の選び方を以下にまとめました。
- ワイド
→ 最も当たりやすい。まずは「当てる楽しさ」を体感。 - 枠連
→ 枠を当てる感覚で、多少の予想ミスをカバーできる。 - 馬連
→ 精度が求められるが、配当が高く達成感も大きい。
このように段階を踏んで馬券選びを進めれば、自然と競馬の予想力が身につきます。最初から無理に高配当を狙うより、確実に当てる経験を積むことが、長く楽しむための近道だと考えられます。
馬連と枠連の違いを理解するための総まとめ
- 馬連は1着と2着の馬を順不同で当てる馬券
- 枠連は1着と2着の枠を当てれば的中する馬券
- 馬連は馬をピンポイントで選ぶ必要がある
- 枠連は枠単位で当てるため的中範囲が広い
- 馬連は配当が高めになりやすい
- 枠連は同枠決着でも当たる特性がある
- ワイドは3着以内に入れば当たりで最も当てやすい
- 馬連とワイドは同じ馬番号を使うが的中条件が異なる
- 枠連単という馬券は存在せず混同に注意が必要
- 枠連ボックスは複数枠を選んで的中範囲を広げられる
- 馬連は予想精度が高い人に好まれる傾向がある
- 枠連は混戦や枠に偏りがあるレースで選ばれやすい
- 馬券の選び方はワイド→枠連→馬連の順で覚えるのが無理がない
- 馬連は収益性を重視する人に向いている
- 枠連は的中率と予想の簡便さを求める初心者に適している
参考文献:国内競馬における不確実性仮説の検証